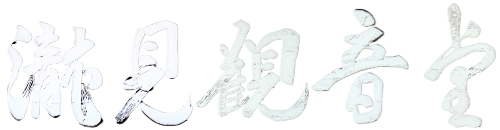瀧見観音堂(浄明寺)は、埼玉県新座市石神にある単立寺院です。その歴史は宝永年間(1704~1710)に遡ります。この地にて観音菩薩の銅像と「瀧山浄名寺」と刻まれた鐸(すず)が掘り出されたことをきっかけに、黄檗宗の僧を招いて庵を建立したのが始まりと伝えられています。
瀧見観音の由来
新編武蔵風土記稿によると、かつて石神村の小名清水という場所で、夜な夜な光を放つ不思議な現象が起こっていました。村人たちは当初、妖狐の仕業ではないかと恐れていましたが、光が絶えず続いたため、相談のうえ光の源を掘り返したところ、そこから銅製の観音像と鐸(すず)が発見されました。
この鐸には「瀧山浄名寺」と刻まれており、村人たちは観音さまの不思議なご加護を感じ、四方に堂を建ててこの像を安置しました。そして、黄檗宗の僧を庵主として迎え、お堂を守ることとなったのです。
その後、観音さまの由来が幕府に報告され、かつて唐(中国)から渡ってきた三体の観音像のうち、行方不明になっていた一体がこの像ではないかと言われ、村に正式に預け置かれることとなりました。
しかし、時代の流れの中で堂宇は破却されることもありました。さらに、村の民家で火災が発生し、四軒が焼失、住人の多くが亡くなるという悲劇も起こります。これを憐れんだ代官が、亡き人々の追善供養のために新たに堂を建立し、観音像を安置するよう命じ、そこに道心ある者を住まわせて堂を守らせたと伝えられています。
現在の瀧見観音堂
このように長い歴史を持つ瀧見観音堂は、地域の信仰の場として親しまれてきました。現在も、毎月18日に観音講を開催し、観音経をお唱えすることで観音さまとのご縁を深めています。また、坐禅会や仏教の学びの場を提供し、静かに自らと向き合う機会を大切にしています。
過去の出来事に思いを馳せながら、現代に生きる私たちが心を整え、仏縁を深める場所として、瀧見観音堂はこれからも皆さまとともに歩んでいきます。どうぞお気軽にお参りください。